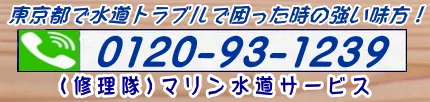水道用語収録一覧:緩速ろ過法

掲載水道用語
緩速ろ過法
緩速ろ過法は、水処理技術の一つであり水中の異物や微生物を除去するために用いられる方法の一つです。この方法は、水を砂や砂利の層を通してゆっくりと流すことで懸濁物や微生物を濾過する原理に基づき以下で説明します。
●原理
・緩速ろ過法は、多孔質の砂や砂利の層を水が通ることで微粒子や異物を物理的に遮断し濾過する原理に基づいています。
・水が砂や砂利の層を通る際、微粒子や異物は層の間隙にとどまり浄化された水は層を通過して取り出されます。
●工程
・準備工程; 砂や砂利を適切に洗浄し緩速ろ過装置を準備します。
・濾過工程; 水を砂や砂利の層を通してゆっくりと流し異物や微生物を除去します。
・取り出し工程; 処理された水を取り出し次の工程へ進みます。
●利点
・単純で低コスト; 緩速ろ過法は比較的簡単で低コストで導入・運用ができるためリソースが限られた地域や緊急時の水処理に適しています。
・効果的な濾過; 砂や砂利の層を通してゆっくりと流すことで微生物や異物を効果的に除去します。
●制限と注意点
・濾過速度が遅いため、大量の水を処理する際に時間がかかります。
・濾過後の水質は砂や砂利の品質、清潔度に依存するためこれらの管理が重要です。
緩速ろ過法は、特にリモートな地域や非常時において緊急の飲料水確保に有用です。ただし、効率性や処理量に制限があるため適切な選択肢として考慮される必要があります。
緩速ろ過法の仕組みについて
緩速ろ過法の仕組みは、原水を砂や砂利などで構成されたろ材層の上にゆっくりと流入させ重力によって自然に透過させることで水中の濁質や細菌などを物理的、生物的に除去する浄水方法であり、その基本的な構造は、上部に原水をためる流入池、中心部に厚さ約90センチから100センチの細粒砂層、その下に粗い砂や砕石などを敷いた支持層、さらに最下層に水を集める集水管を設けたシンプルな設計となっており運転中には砂層表面に生物膜と呼ばれる微生物の層が自然に形成され、この層が有機物や細菌類を分解、吸着する主要な役割を担い水が通過する過程では、物理的なろ過作用だけでなく、この生物膜による生物学的浄化作用が加わることで高い水質改善効果を発揮する。加えて原水の流速は1日あたり1平方メートルあたり2〜5立方メートルと極めて遅く設定されており、この低速かつ連続的な流れがろ材中における接触時間を長くし微生物の活動を活性化させるとともに、ろ過能力の持続にも寄与するため長期間にわたって安定した浄水処理が可能となるが、ろ材表面に付着した汚れが蓄積してろ過速度が低下した際には、ろ層の上部を数センチ削り取る掻き取り作業によって機能を回復させるという保守管理が行われry。このように緩速ろ過法は、動力や薬品の使用を最小限に抑えつつも自然の力を利用して安全で美味しい水を供給する環境負荷の少ない持続可能な水処理技術である。